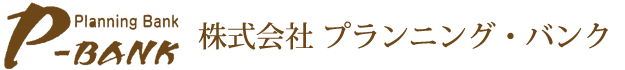耳よりコラム
医療機関における雇用の固定化と流動化のリスク分析
CFP 須磨 光
医療機関において確保が困難で雇用の優先度が高い人材も、職種や資格のカテゴリー別に大きく二分されている。人材確保の難易度が高く、採用までに時間とコストを要する職種と、供給数自体が少なく雇用の流動性に乏しい職種とに分けることができる。前者の代表例は、医科での看護職員(正看護師・准看護師)と歯科での歯科衛生士となり、後者は生殖医療での胚培養士や眼科における視能訓練士等を挙げることができる。
看護師の有効求人倍率は2018年度2.35倍、2019年度2.31倍、2020年度2.05倍、2021年度2.12倍、2022年度2.20倍と、職業計での有効求人倍率2018年度1.46倍、2019年度1.41倍、2020年度1.01倍、2021年度1.05倍、2022年度1.19倍、と比較しても、常に供給を需要が2倍以上上回っていて、慢性的な看護師不足を示している。特に2020年度以降は、緩やかな景気回復や賃上げ傾向を受けて雇用の流動化が活発となり、全体の有効求人倍率が大幅な改善を見せた中で看護職員は高止まりを続け、職業計と比して2倍近い倍率となっており看護職員の不足傾向は続いている。*1
さらに2040年に向けた今後の需給予測についても、2018年度の看護職員の需要推計が177.8万人だったのに対して、2025年度には194.5万人、2030年度は203.2万人と初の200万人台を突破し、その後も増加を続け2035年度208.7万人、2040年度には210.1万人に達するとされている。*2需要については、高齢化社会の中で訪問看護を含む介護分野での看護職員のニーズがますます増加し、供給側も加速する少子化が足を引っ張る悪循環に陥っている。抜本的な少子化対策が施されない以上、外国人労働者や高齢者の看護分野への活用へとさらなる門戸を開いたり、看護ロボットなどの技術革新を進めるしか道は残されていない。
こうした状況は、歯科衛生士においても同様だ。歯科衛生士の2022年度における有効求人倍率は3.39倍と、看護職員と比してもさらに人手不足が深刻な状況となっている。歯科においても訪問診療や介護施設での歯科衛生士の需要は年々増しており、今後も増加の一途を辿るものと考えられる。一定の研修をクリアした経験豊富な歯科助手に、歯科衛生士業務の一端を担わせるなど資格制度改革や緩和策も必要ではないだろうか。無資格者にグレーゾーンとして違法行為をさせる歯科医院も少なくない現状を鑑みると、新たな制度を策定し管理した方が有益と考える。
都道府県別の看護職員の2025年度における需給予測は、佐賀や宮崎といった人口減少地域では供給が需要を上回っているが、東京・神奈川・千葉・埼玉といった首都圏においては、需要に対して供給が大幅に不足している状況だ。大阪・奈良・京都・広島といった関西・近畿・中国地方の主要都市圏でも同様に需要に対して供給が追い付かず、今後も看護職員不足が続くと予測されている。*3 但し、こうした需給バランスの悪い地域であっても一律に不足するわけではなく求職者の職場を選別する目は一層厳しくなり、人気が分かれることになるだろう。人材確保や流出防止のためには、賃金を含む待遇改善を進める必要に迫られている。
一方で資格を必要としない受付・事務などの一般職の需給バランスはどうだろうか。全体の有効求人倍率が1倍程度に改善したこともあり、ハローワークなどでの求人や新卒での採用も比較的容易な状況にある。募集を出せば、何らかのレスポンスは期待できる。そこで理事長やオーナー院長といった経営者には、補充が容易として無資格職種を軽視する傾向があることは否めない。結果として待遇改善が遅れ、相対的に離職率も高くなっているのが現状だ。それどころか、昇給での人件費の高騰を嫌い、若く安価な初任給で済む職員との入れ替えを意図的もしくは無意識化のうちに進めているケースすら見受けられる。 それでは、雇用を固定し定期昇給による人件費総額が年々大きくなるケースと、人の入れ替えで人件費を抑制した場合での人件費だけではない実際のコスト面で比較するとどちらが有利となるのだろうか。(株)リクルート就職未来研究所の「就職白書2020」によれば、2019年の新卒採用1人当たり平均採用コストは936,000であり、この採用コストの中には求人や教育に係る人件費などの内部コストと、求人広告費や紹介会社への報酬などの外部コストがある。300人未満の中小企業における新卒者教育に係るコストは平均500,000円とのデータもあり、頻繁な離職と採用の繰り返しは目先の賃金以上にトータルでのコストは高くつくことになる。*4 また、間接的なマイナスの影響も見逃せない。新人の教育を繰り返し行わなければならない教育担当者や、事務と看護職といった他部署であったとしても、仕事上の連携を再構築しなければならない既存職員の負担増を見逃すと、負の連鎖に陥りかねない。さらには人間関係の希薄化に伴う職場での居心地の悪さといった環境変化から、本来去ってほしくない必要な人材まで流出しかねないリスクをはらんでいる。 さらには、内部のことだけではなく入院・通院している患者に対しても、スタッフが頻繁に入れ替わることは悪い印象を与え、長い目で見ると患者数や収益そのものにも悪影響を及ぼしかねない点についても注意が必要である。
とはいっても、離職を恐れるあまり歯止めなく人件費を増大させることは、収益が減少に転じた際の人件費比率が経営上の足かせともなり、人件費総額の抑制にも目配りしなければならない。離職リスクの高い職員、必要不可欠な職員、離職するリスクが少ない職員など職種・年齢別に評価し、適切な人件費を構築するべきである。基本給を一律の昇給率で昇給させる従来型の昇給制度や賞与額の査定制度は雇用の安定化と人件費総額の適正化には適しておらず、職員一人一人を細かく査定・評価するシステムを構築する必要がある。
(参照資料) *1 「職業安定業務統計」厚生労働省 *2 「2040年を見据えた社会保障の将来見通し(議論の素材)」から「医療推計バックデータ」の現状投影ベースを用いた推計 *3 「医療従事者の需給に関する検討会」看護職員需給分科会 中間とりまとめ(概要) *4 「就職白書2020」(株)リクルート就職未来研究所
成年後見制度の実情
行政書士 加藤 修
「老病死」は厄介ものである。だが、生まれたが為に、生きているが為に存するものである以上、誰もが避けては通れない。大国の元大統領がアルツハイマー病だったと聞いても、「そんなこともあるだろう」と誰もが納得するのである。しかし、こと自分のこととなると、そうスンナリとは認めたがらないのが日本人の常であるらしい。
判断能力が不十分な人達を保護し支援するのが成年後見制度であるわけだが、我が国では自分から手を挙げて助けを求める人は先ずいない。ほぼ完全に判断能力を失っていれば、その受け皿さえあれば、法定後見が可能である。全て本人以外の者の代理によって事が運ぶからである。
問題なのは、まだ本人に幾分かの判断能力が残っているか、あるいは健常者に比して若干判断能力が不十分であると思われる程度の場合である。そんな場合、大抵本人は自分の判断能力が不完全であることを認めたがらない。薄々自分自身の記憶能力や判断能力の衰えに気づいていても、それを認めることはできない。「ひとの世話になる」ことは、即「ひとに迷惑をかける」ことである。・・・そんな思いに煩わされるのは戦前戦後を生き抜いてきた日本人の底流に息づく倫理観のなせる業なのか。長寿社会においては恥の文化もまた延命したのである。特に大方の老人は短期記憶ではなく長期記憶の中に生存しているのであるから。
しかし、判断能力があると診断された場合、本人は判断しなければならない。決断を迫られることもあるわけである・・・「施設への入所はどうするのか?」「アパートの管理は誰にまかせるのか?」・・・老人の記憶は反芻する・・・ひょっとすると別れた妻が今住んでいる家に帰ってくるかもしれない。音信不通になっている息子と一緒に・・・。巡り巡って決断不能のまま、公証人は既に証書を作成し、契約締結の為に施設へ出張した時点で任意後見契約は不成立。・・・そのような例は決して希ではないのである。
悪徳商法に既に何度かひっかかっていても、それを認めるにはプライドが許さないお婆さん。自分が持っている財産が並みのものではないことを知っていて、算盤ばかり弾いているにも拘わらず、その財産の本来の価値を判断出来ないで不安ばかりをつのらせ、けれども誰一人として信じることが出来ないでいるお爺さん。・・・民生委員や福祉関係者は、毎日そのような人々と接しているのが現状なのだ。
冒頭「老病死」と言った。「死」については遺言や保険によって安心を得ることができる。「老・病(精神的及び知的)」に対応するものが「成年後見制度」であるわけだが、前述したように、幾分でも判断能力を欠いてからでは、色々とやっかいなことが起きる可能性が強い。
生まれつきの知的障害者の方等、善後策を尽すしかない場合は別として、できれば、判断能力が完全である時点において任意後見契約を締結しておくのがベストだと思う。
お金の話し
CFP 須磨 光
お金は物々交換を仲介する目的で作られた。大昔、人々が自給自足で暮らしていた頃、足りないモノは直接、物々交換で手に入れていた。しかし、こちらは相手の持っているモノが欲しいが、相手はこちらの持ちモノを必要としていないかもしれない。必ずしも希望が一致するとは限らないのだ。そこで、物々交換を仲介する役割としてお金が必要となる。お金には「交換・支払いの手段」としての機能と、異なる価値の様々なモノを同じ単位で測る「価値の尺度」としての機能、時間が経てばその価値を失ってしまうモノもあり、お金に換えておくことで価値を保つ「価値の保存・貯蓄手段」としての機能がある。
このようなモノとモノとの仲介役を果たすためには、お金自体に信用力が求められる。そのため、希少価値の高い金貨や銀貨が用いられてきたのだ。紙切れに過ぎない紙幣の場合、その紙幣をいつでも「金」と交換することができると国が保証していた。このような「兌換紙幣」の場合、その国の保有する金の量を超えて紙幣を発行することができない。こうした通貨の発行量が、保有する金の量に制限される制度が「金本位制」である。日本においては1941年に、軍需による資金不足が生じ、翌年、金の保有量に制限されずに発行限度額を大蔵大臣(現、財務大臣)が定めることができるとした「日本銀行法」が制定され、紙幣の名称はそれまでの「日本銀行交換券」から「日本銀行券」へと改められた。このような金と交換できない紙幣を「不換紙幣」と呼ぶ。
現在、日本国内で発行されている紙幣は、1万円、5千円、2千円、千円の4種類がある。2千円札はとんと見かけなくなりほとんど流通していないが、当然に使用することができる。新紙幣に切り替わっても、旧紙幣も使うことが可能だ。回収が進みほとんど流通していないが、伊藤博文の千円札や板垣退助の百円札、二宮尊徳の一円札など他にも15種類の紙幣が今でも立派に通用している。
遺言について
普通の方式による遺言には、大きく分けて3種類あります。
①自筆証書
②秘密証書
③公正証書
それぞれに厳格な要件がありますが大きく異なるのは、このうち①、②の遺言については、遺言の保管者は相続の開始を知った後、遅滞なくこれを裁判所に提出して検認手続きを経なければならないのに対し、③公正証書遺言のみは、その必要がないということです。従って③では、相続が開始すれば直ちにその遺言書に基づいて不動産の登記申請が可能となります。
もっとも、この相続、または遺贈登記手続きによって遺留分権利者が自己の遺留分を侵害された場合は、当該登記のなされた後でも遺留分に基づく減殺請求権を行使して、侵害された分を取り戻すことは可能ですが・・・。但し、③の方式によって同じように遺言されてはいても、預金等については金融機関によっては遺言書のみによって払戻し請求に応じてくれないところがあります。
すなわち、金融機関独自の書面に法定相続人全員の署名、実印での捺印を求める金融機関があるわけです。不動産と異なり、金銭は消費されれば回復しにくいことからこのような取り扱いをしているのかもしれませんが、せっかくの遺言書の効能を減殺している気がしてなりません。法律と実務の微妙な関係のお話です。
マイナス金利の不思議
CFP 須磨 光
講義に使用したテキストに次のような文書が記載されていた。
「名目金利よりも物価上昇率が大きいと、実質金利はマイナスとなる。しかし、名目金利がマイナスとなることは理論上あり得ない(お金を預けたのに逆に利息を取られたのでは、お金を預ける人がいなくなるため)」
これを読み上げた後、「これは誤りですね。名目金利でもマイナス金利は発生しています」と解説した。 預金残高が一定の額を割り込むと口座管理手数料などがかかり、実質的にマイナス金利となってしまう仮性マイナス金利だけではなく、利息を払ってお金を借りてもらう摩訶不思議な取引が頻繁に行われているのだ。いくら低金利といっても、まさかお金を預けると逆に利息を取られてしまうとは思いもよらないのが普通だ。
ところが、金融機関同士で短期の資金を取引しているコール市場においては、利息を付けて借りてもらうマイナス金利取引が度々発生している。
これは、相次ぐソブリン格付けのノッチダウンに見られるように、日本という国の信用力が地盤沈下していることに起因している。国や銀行の信用力が低いと、その信用力に応じたリスクプレミアムを要求されることになる。
基軸通貨として世界の貿易決済に用いられている米ドルを調達するために、日本の銀行は一定期間、円とドルを交換する為替スワップを行っている。その際に円や邦銀の信用力が低いという理由で、通常の為替レートに上乗せするリスクプレミアムを要求されているのだ。こうして上乗せ金利をもらって預かることになった外銀は、その円を他に貸し出そうとする。これまでは日銀当座預金に預けていたのだが、日本国の信用力低下を受けて外銀本部が日銀当座預金残高に制限を設けるようになった。そこで、信用力の高い他の外銀に利息を付けてまで預けているのがマイナス金利の実態だ。邦銀からの上乗せ金利で、これでも十分利ザヤが稼げる寸法だ。
ジカンのモンダイ
CFP 須磨 光
フィブリノゲンという血液製剤によってC型肝炎に感染した薬害被害者が多発している。フィブリノゲンは旧ミドリ十字社が1964年から製造・販売を始めたが、米国では1977年に肝炎発生のリスクが高いとしてFDA(食品医薬品局)が製造承認を取り消している。日本では米国の承認取り消し後も大量に販売を続け、1980年以降だけを見ても約28万人に投与され、少なくとも1万人以上がC型肝炎に感染したと推計されている。
フィブリノゲンによる薬害被害が表面化してきた1987年に書かれた「フィブリノゲン肝炎調査厚生省中間報告の件」と題する書面の中には、当時の厚生省薬務局安全課医薬品副作用情報室室長がミドリ十字に対して、「血液製剤が使われた場合の患者の不利益(C型肝炎への感染)について、やむをえないことを述べている文献を用意できないか」「現在の学問レベルでは原因究明、予知は無理との文献はないか」と注文し、「こういうこと(C型肝炎に感染するリスク)が血液製剤の特性である。良くするには研究開発するしか手がないということで肯定していく。即ち努力してもここまでが現状ということでいく」と結論付けている。薬害を監視・指導する立場の厚生省の責任者がこれでは、グルになって被害を拡大させたと非難されても致し方ないだろう。国民の命を犠牲にしてでもかばおうとしたミドリ十字は、厚生省の天下りを積極的に受け入れてきたのだ。
最近、相次いだ雪印や日本ハムによる牛肉買取の偽装事件は、農水省が犯罪を誘発したといえなくもない。当初、マスメディアがこうした偽装行為が行われるのではないかと危惧したにもかかわらず、農水省はと畜証明書を不必要、全箱検査も実施しないとして、中身が何でもフリーパスで買い取るような姿勢を示した。それが一転したのは、雪印食品の取引業者である西宮冷蔵が牛肉偽装を告発したことに端を発している。この倉庫会社の告発がなければ、雪印食品も日本ハムも偽装が表面化することなく、いまだ闇の中にあったのは想像に難くない。
ところが、驚いたことに告発した西宮冷蔵に対して、国土交通省が雪印食品の伝票改ざんを理由に営業停止処分を下そうとしているのだ。まさか告発したことに対する官庁の意趣返しとは思いたくないのだが・・・。その後、11月6日付の新聞の片隅に「雪印の偽装告発、西宮冷蔵廃業へ」と小さく書かれていた。雪印以外の荷主からも取引停止が相次ぎ、業績が悪化したのが理由という。役所が先頭に立ち、よってたかって廃業に追い込むようなことでは、告発に二の足を踏むことになっても当然だ。
今月だけを見ても、広島の第三セクターで、役人の天下り社長が不正経理、業務上横領で逮捕されている他、阪神高速道路公団幹部が公共工事の入札情報を漏らして特定業者に利益供与したとして、公団幹部、工事を落札した建設会社のトップら4人が逮捕、その後も日本道路公団が発注する道路保全工事の入札で談合を繰り返したとして、公正取引委員会が独占禁止法違反でファミリー企業4社に排除勧告を出すなど、役人や元役人による不祥事が相次いでいる。阪神高速道路公団の事件では、工事を落札した建設会社のトップも道路公団からの天下りで、逮捕された4人全員が元役人という構図だ。民間企業にしても、問題となっている業界は「官僚化」というウィルスに侵されている。小泉首相は銀行に対して、「金融機関は大手も中小も官僚化している」と批判し続けている。
こうした銀行は旧大蔵省を始めとする役人天下りの温床でもある。まさに「官僚化」こそが、今の日本経済の病根ともいえるのだ。昔、通産省がホンダやマツダを潰して、トヨタ等大手に吸収させようと画策したことがある。通産省事務次官の横暴に対して、本田宗一郎が皮肉を込めていった言葉が「次官次官と威張るな次官。いなくなるのも時間の問題だ」 当然、全ての官僚が無能というわけではない。創造性豊かな人材がいても、トップが無能ではこれを活用することがかなわない。まさに、次官の問題だ。